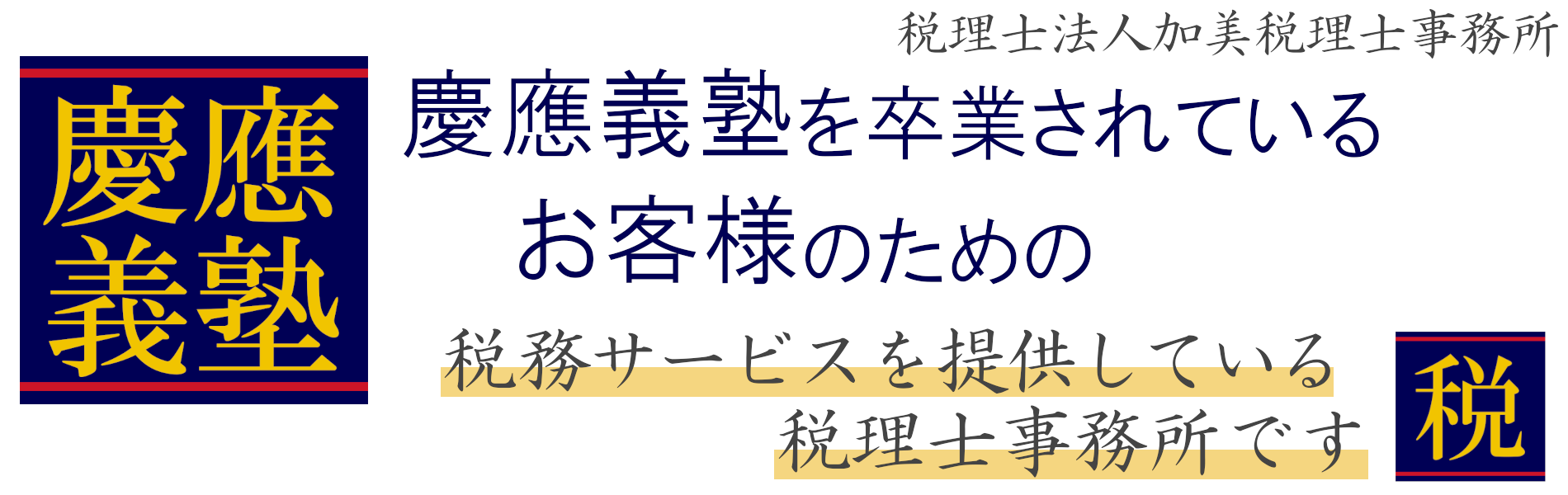ごあいさつ
税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
私は慶應義塾大学経済学部を卒業した税理士です。
こちらのウェブページにお越しいただき誠にありがとうございます。
当税理士事務所では、慶應義塾OB・OGのお客様に向けて法人および個人の税務申告などを承っています。
ご興味がおありでしたら、是非お気軽にお問い合わせください。
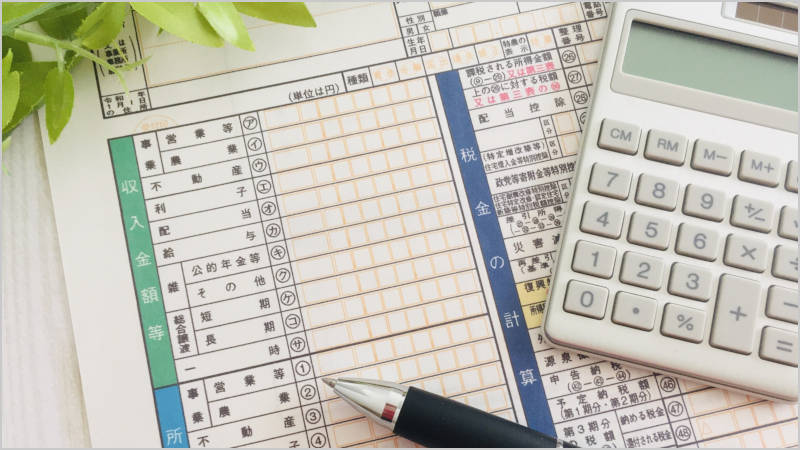
所得税の確定申告を承ります
慶應義塾を卒業されているお客様の所得税の確定申告を承ります。税理士に直接会わずとも申告ができるサービスを実現しています。

法人の税務も承ります
当税理士事務所では、慶應義塾を卒業されているお客様が経営されている法人の税務も承っています。

慶應卒の税理士です
私自身も慶應出身の税理士です。税理士を目指したきっかけ、このヘンテコなウェブページを作った理由、学生時代の思い出などを紹介しています。

慶應義塾と税理士
慶應義塾といえば公認会計士で、税理士は比較的マイナーです。慶應義塾大学の入試と税理士試験の難易度比較やこれから税理士を目指す塾生のためにおすすめルートなどを紹介しています。

日本全国&海外に対応
フルリモートにつき、日本全国どちらのお客様でも対応可能です。海外在住のお客様にもご愛顧いただいています。(日本法人の日本国内における決算申告を承っています。)

Webミーティングに対応
面談もWeb会議システムにて承ります。アプリやアカウントは不要です。初回無料相談もリモートで対応可能です。ご要望があれば直接お会いすることもできます。

法人設立もサポート
現在、個人事業主の方などこれから法人を設立されるお客様のサポートも承ります。提携している司法書士事務所の協力により相場より安く法人を設立できることもあります。
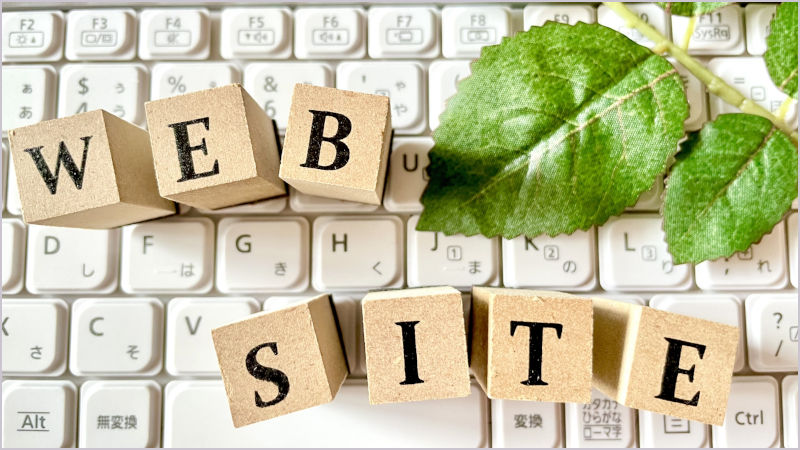
Webサイト作成もサポート
こちらのサイトくらいシンプルな内容のWebサイトであれば格安で構築を支援します。初期費用のみでランニングコストは頂戴しないため安心していただけます。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ料金体系
税理士法人加美税理士事務所の税理士川畑英之と申します。
料金体系は次のとおりです。
サービスごとに標準的な料金・費用を記載しています。
会計ソフトで記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。
弥生会計をご使用されているお客様は特に優遇させていただいています。
【個人の方】
※すべて税抜金額で表示しています。
【顧問契約あり】法人の顧問費用および決算費用
・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
| 法人税等 | 売上高 | |||
| 1000万円以下 | 1000万円超 | 2000万円超 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000万円以下 | ||||
| 顧問報酬 | 月額 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円〜 |
| ①年額換算 | 120,000円 | 144,000円 | 180,000円〜 | |
| ②決算報酬 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円〜 | |
| 基本報酬額①+② | 180,000円 | 204,000円 | 240,000円〜 | |
上記が基本的な費用額です。
ただし、会計ソフトをお使いでないお客様については、領収書や請求書などの証憑の数が多い場合は下記の料金を別途加算させていただきます。
| 証憑の処理件数による加算額 | 証憑の処理件数 | |
| 500件以下 | 500件超 | |
|---|---|---|
| 1件当たりの加算額 | 0円 | 100円 |
こちらの処理件数は、補助簿をお客様ご自身でご作成いただく場合は大幅に抑えることができます。
例えば100枚のレシートを1枚の補助簿にまとめたときは、その処理件数は1件となります。
大した手間ではないため、領収書などが多い方にはこちらの方法をおすすめしています。
補助簿の作成方法については必要なタイミングで別途ご案内差し上げます。
・消費税
弥生会計で記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。
| 消費税 | 納税額(還付額) | ||
| 100万円以下 | 100万円超 | ||
|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 30,000円 | 40,000円〜 | |
| 原則課税 | 一括比例配分 | 40,000円 | 50,000円〜 |
| 全額控除 | 40,000円 | 50,000円〜 | |
| 個別対応 | 50,000円 | 60,000円〜 | |
| 還付申告 | 60,000円 | 70,000円〜 | |
消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える法人は、将来的に課税事業者になる可能性があります。
収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。
オプション料金
一定の場合にはその他の税務イベントが発生します。
その際は、別途オプションをお申込みいただくことができます。
当該オプション料金・費用についてはこちらのページをご覧ください。
【年一決算のみ】法人の決算費用
・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
| 法人税等 | 売上高 | |||
| 1000万円以下 | 1000万円超 | 2000万円超 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000万円以下 | ||||
| 年一決算報酬 | 150,000円 | 180,000円 | 200,000円〜 | |
・消費税
弥生会計で記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。
| 消費税 | 納税額(還付額) | ||
| 100万円以下 | 100万円超 | ||
|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 30,000円 | 40,000円〜 | |
| 原則課税 | 一括比例配分 | 40,000円 | 50,000円〜 |
| 全額控除 | 40,000円 | 50,000円〜 | |
| 個別対応 | 50,000円 | 60,000円〜 | |
| 還付申告 | 60,000円 | 70,000円〜 | |
消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える法人は、将来的に課税事業者になる可能性があります。
収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。
法人設立費用
| 法人設立費用 | |
|---|---|
| 合同会社 | 約13万円 |
| 株式会社 | 約28万円 |
法人設立サポートを適用した場合はもっと安く済むことがあります。
個人の確定申告費用
・所得税
基本的には、従量制です。
例外として金額の規模によっても変動する場合があります。
(例:事業所得、不動産所得、雑所得、譲渡所得)
| 所得税 | |
|---|---|
| 基本料金 | 30,000円 |
| 給与所得(2ヵ所目以降がある場合) | 2,000円/1件 |
| 事業所得 | 60,000円~ |
| 雑所得 | 30,000円~ |
| 不動産所得 | 60,000円~ |
| 一時所得 | 都度見積り |
| 譲渡所得 | 都度見積り |
| 配当所得 | 都度見積り |
| 利子所得 | 都度見積り |
・消費税
| 消費税 | 納税額(還付額) | ||
| 100万円以下 | 100万円超 | ||
|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 30,000円 | 40,000円〜 | |
| 原則課税 | 一括比例配分 | 40,000円 | 50,000円〜 |
| 全額控除 | 40,000円 | 50,000円〜 | |
| 個別対応 | 50,000円 | 60,000円〜 | |
| 還付申告 | 60,000円 | 70,000円〜 | |
消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える方は、将来的に課税事業者になる可能性があります。
事業収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせお問い合わせから申告までの流れ
青字の項目は税理士の担当です。
- お問い合わせ
- お電話、メール、Chatworkのいずれかでお問い合わせください。
※営業時間外の場合はメールかChatworkでお問い合わせいただきますようお願いします。
- Webミーティングの日程調整&参考資料のご送付
- Webミーティングの日程を調整します。
また、過年度の確定申告書や帳簿、定款、登記簿謄本など必要となるものを事前にデータ又は郵送でお送りいただきます。
- Webミーティング(初回無料相談)
- 事業の内容、税務トピック、経理状況をお聞きして、作業ボリューム及び料金を見積もります。
また、税理士とお客様のそれぞれにおいて担当すべき作業を明確に整理します。
- 契約書のご締結&着手金のお振込み
- 契約書をお送りします。
内容に問題がなければご署名ご捺印のうえご返送していただきます。
※契約書は書面、電子のどちらでも対応可能です。(電子契約の方が圧倒的に早いです。)
法人設立に関する届出書一式を提出するなど一定の場合は、併せて着手金を当方の口座にお振込みいただくことがございます。
- 資料データのご格納(or 紙でのご郵送)
- 資料データをクラウドストレージにご格納いただきます。
または紙のままご郵送いただきます。
- 帳簿作成(帳簿が必要なお客様のみ)
- お送りいただいた資料に基づいて当方で帳簿を作成していきます。
不明な点があればメールやChatworkでご連絡させていただきます。
- 決算のご承認(帳簿が必要なお客様のみ)
- 帳簿が完成すると決算書も完成します。
決算書の内容に問題がなければご承認していただきます。
内容については、Webミーティングまたは文面でご説明を申し上げます。
- 確定申告書の作成
- (ご承認いただいた決算書に基づいて)当方で確定申告書を作成します。
- 確定申告書のご承認
- 確定申告書の内容に問題がなければご承認していただきます。
- 電子申告
- 当方で確定申告書を電子申告にて提出します。
- 税金のご納付
- 電子納付または納付書による窓口での納付をしていただきます。
電子納付の場合→電子納付情報を当方からお知らせします。
窓口納付の場合→納付書を当方から郵送します。
- 決算報酬のお振込み
- 決算報酬を当方の口座にお振込みいただきます。
- 成果物の納品
- 確定申告書一式、決算書(※)、総勘定元帳(※)をデータでご送信します。
※帳簿が必要なお客様のみ
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ慶應義塾を卒業した税理士です
税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
私は慶應義塾大学経済学部を卒業した税理士です。
こちらのWebページにお越しいただき誠にありがとうございます。
当税理士事務所では、慶應義塾OB・OGのお客様に向けて法人および個人の税務申告などを承っています。
ご興味があおりでしたらお気軽にお問い合わせください。
こちらのページには私の人となりがなんとなく伝わるようなことを徒然と書いております。
もしもお暇でしたらお読みいただけると幸いです。
税理士を目指したきっかけ
私が税理士を目指したきっかけについてお話します。
税理士を目指すことにしたのは、23歳の頃です。
慶應義塾大学を卒業し、新卒で入社したベンチャー企業をわずか8ヵ月で辞めたときです。
その会社を退職した日の夜にサークル時代の先輩と飲んだときに、その先輩が税理士を目指すことを強く勧めてくれました。
先輩も当時は税理士を目指して勉強していました。
彼は一流企業に勤務していましたが激務のためいつまでも働き続けるのは難しいと感じていたからです。
それまで私は税理士になろうなどと考えたことは微塵もありませんでした。
しかし幸いにもその会社で簿記3級を取得させられていたため、税理士を志す下地が少しだけですが出来上がっていました。
当時はリーマンショックがあった頃で求人状況が芳しくなく、すぐに再就職するには厳しい環境でした。
そのため手に職をつけるために税理士になることを決意しました。
さらに税理士試験は科目合格制であるため、何科目か合格していれば再就職が容易だったことも税理士を目指す積極的な理由となりました。
また、学生の頃から独立志向が強く、自ら起業して活躍していきたいという願望がありました。
ベンチャー企業に就職したのはそのような理由からでした。
税理士になれば税理士として独立することもできますし、他の業種で起業したとしても税務会計の知識が大いに役立ちます。
上記の先輩はこれらのこと及び私のことをよく理解していたからこそ、強く税理士を勧めてくれたのでした。
あのとき先輩が私に税理士を勧めてくれなかったら今の私はないでしょう。
先輩にはとても感謝しています。
なお、先輩ご本人は現在も当時と同じ会社に勤めていて大いに活躍されているようです。
税理士になってよかったと思うこと
晴れて税理士になることができた今になって思うことは、税理士を目指してよかったということです。
このようによかったと思える理由としては、自分は税理士に向いていたと感じているからです。
会計学も法学も自分には合っていると思っています。
また、お客様から頼りにしていただけるという点でもやりがいを感じています。
会計学は勉強を始める前から興味があり自分に合うと考えていました。
一方、法学には当初苦手意識がありました。
法学は、覚えることが多そうだし細々としていて面倒そうだと感じていたからです。
正直なところ学部時代は、法学部の人は文系なのに勉強が大変そうで可哀そうだなくらいに思っていました。
しかし実際に勉強を始めてみると法学は思いのほかおもしろく勉強が捗りました。
色々な条文や文言などを組み合わせて解釈していくところが自分にはぴったりでした。
さらに税法はお金に直接関係することであるため、知れば得をするという感覚がありました。
また、税理士はその立場上、お客様に寄り添うことができます。
この点では似たような職業である公認会計士や国税専門官と異なります。
公認会計士は会社を監査する立場であるため細かいことをガミガミ言ってくる連中だとお客様から思われがちです。
国税専門官にいたっては国のために頑張って税金を徴収しているのに、残念ながら国民からは税金を搾り取っていく連中だと思われることもあります。
これらと比較すると税理士は、適正な納税を促しつつも節税案を提案するなどして、お客様の味方として活躍できます。
そのためお客様から信頼いただけたり感謝していただけることが多いです。
このような理由でとてもやりがいを感じています。
このヘンテコなWebページを作った理由
このページをご覧いただいている皆様にお聞きしたいことがあります。
よくもまあ、こんな変なWebページを作ったなぁと思いませんか?
自分でもそう思っています。
慶應義塾のOB・OGの方がご覧になっても恥ずかしくて見ていられないというお気持ちになっているかと思います。
不快に思われる方がいらっしゃいましたら誠に申し訳ございません。
ここではそのような世にも奇妙なこちらのWebページを作成した理由について紹介したいと思います。
ズバリ集客のためです
このヘンテコなWebページを作ってしまった理由は、ズバリ集客のためです。
マーケティングのコンセプト
現在のところ、私のメインの集客方法はWebページによるものです。
Webページには様々な規模のものがありますが、ごく小規模なものです。
これを無数に作成しています。
また、検索エンジンに広告を載せるのではなく、検索順の上位に表示されることによってクリックしていただくことを目論んでいます。
さらに検索キーワードは人気があるものではなくニッチなものを選ぶことにより、他との競争をできるだけ避けています。
このような集客方法を採っている理由は次の通りです。
Webページ1件を外注により制作してもらうと初期費用で数十万円、維持費用で毎月数千円以上がかかります。
このミニマムコストの高さにより、Webページを外注する場合にはそれなりの集客が高い可能性で見込める必要があります。
それなりの集客が高い可能性で見込めるということは、対象とする検索キーワードの検索数が多いか、または売上単価が高いかのどちらかです。
そのような検索キーワードのマーケットは必然的に競争が熾烈になります。
その激しい競争を勝ち抜くためには少しでも多く広告料を支払うか、少しでも上の検索順位に表示されるようにコンテンツを作りこむ必要があります。
人気の検索キーワードにおいて検索順の上位で表示されるコンテンツを作りこむ場合にはどのくらいのコンテンツ量が目安かというと、おおよそ100ページ以上といわれています。
以上のように、Webページを外注で制作してもらう場合には、ある程度のコストと作業量を覚悟しなくてはなりません。
ゆえに、賢明な人は成果が見込めるかどうかもわからないニッチな検索キーワードを対象としたWebページを外注するという決断にはなかなか至らないわけです。
しかしながら、ニッチな検索キーワードを対象としたWebページも多く存在します。
その多くはシステムエンジニアなどのIT技術に長けていて自らWebページを作成できる個人か、そういった方を抱えている会社などの組織が手間暇かけずサクッと作り上げたものだと私は考えています。
手間暇かけずサクッとというのはニッチな検索キーワードであれば、それほどコンテンツを作りこむ必要がないからです。
ところで、検索エンジンの上位に表示されるようなWebページを自作できる税理士は多くはいないと思います。
ということは、「税理士が集客のために作ったニッチな検索キーワードを対象としたWebページ」はそれほど存在していないと推測されます。
そこで私は思い立ったのです。
検索エンジンの上位に表示されるようなWebページを自らの手で作り上げることができる税理士になろうと。
そして「ニッチな検索キーワードを対象としたWebページ」を量産してやろうと。
今まさにその思い付きを実行しているところです。
ちなみにこちらの「慶應税理士」というWebページは、低コスト、低作業量で作成および維持することができています。
このような簡易的なWebページであるため、思うように集客ができなくてもまあ構わないかなという気持ちでいます。
ただ、少しでもご興味をもっていただける慶應義塾のOB・OGの方と巡り会えたら幸いです。
お気軽なWebページですので、お気軽にお問合せいただければと思います。
ここまでの文章をお読みいただいてなんとなくおわかりいただけているかと思いますが、私はお客様にとって肩の力を入れる必要などまったくないタイプの税理士です。
慶應義塾のOB・OGの方であればなおさらリラックスしてご連絡していただきたいです。
検索キーワードは「慶應 税理士」
上で触れたように、私、税理士川畑英之はニッチな検索ワードを対象としたWebページにより集客をはかっています。
こちらのWebページは「慶應 税理士」という検索キーワードからの流入を期待して作成したものです。
ここでは、なぜこのキーワードを対象としたWebページを作成したのか紹介したいと思います。
慶應義塾OB・OGの方に対してはもはや説明不要かと思いますが、慶應出身の人は愛校心が強い方が多いですよね。
外部の人からは異様に感じるほどでしょう。
三田会が日本で最も影響力のある大学OBOG会であるということはよく知られています。
実際、私もこれまでの人生において慶應義塾OBの結びつきの強さを感じる機会が多くありました。
まずは、新卒で入社したベンチャー企業でのお話です。
その会社の社長は私より一回りほど上の慶應出身の方でした。
最終面接で彼から直接内定をいただきました。
次に、税理士試験に合格した後に就職したデロイトでも慶應出身のパートナーに大変お世話になりました。
彼が私を採用することを後押ししてくださったようです。
何度も飲みに連れていっていただきましたし、とてもかわいがってくださったことは忘れません。
さらに、社会人になってから結成したフットサルチームのメンバーも皆慶應出身です。
数名のメンバーの知り合いを年齢を問わず寄せ集めて作ったチームですが、とても結束力が強いと思います。
社会人になってから人とここまで仲良くなれるとは考えてもみなかったのでうれしい驚きがありました。
慶應出身の人同士で集まるとどこか学生気分に戻れるような空気感があるのかもしれません。
そして、税理士として集客するようになってからニッチな検索キーワード(こちらの「慶應 税理士」とは別のもの)で私を見つけていただき、最初に顧問契約を結んでくださった方も慶應出身です。
初回無料面談の際に簡単なアンケートにお答えいただいています。
その中で当事務所にお問い合わせていただくにあたって、Webページのどこが決め手になったのかをお聞きしています。
「いや、実は僕も慶應出身なんですよ。」とその方がおっしゃっていたのをよく覚えています。
しかもその方は驚くような著名人なのです!
彼のメディアでの露出やSNSでのフォロワー数と、私が作ったWebページのニッチさとのギャップといったらまさに月とすっぽんです。
彼と巡り会えたことで、自分のマーケティングセンスも捨てたものではないと自信を持つことができました。
以上のように私自身も慶應義塾OB・OGのつながりの強さを実感してきました。
そこで、脳裏にうっすらと「慶應 税理士」という検索キーワードが浮かんできていたわけです。
税理士を探すにあたって、せっかくなら慶應出身の人がいいなと考える方がいらっしゃるのではないかと。
しかしながら、そのようなWebページを作るのは厚かましいかと思い気が進みませんでした。
そのようなわけでこの「慶應 税理士」というコンセプトは棚上げしていたわけですが、その考えを改めてこのWebページを作成する決意をした出来事がありました。
それは「慶應義塾高校野球部」の甲子園での活躍、ではなく彼らを応援するスタンドの熱狂ぶりをテレビ画面ごしに見たときでした。
正直なところ、私自身はそこまで慶應義塾に対する愛校心が強いわけではありません。
また、私が慶應義塾に入ったのは大学からであるため、慶應義塾高校に対してはほとんど思い入れもありません。
そんな私からしてみれば、あのときの甲子園のスタンドの熱狂的な雰囲気は異様なものに映りました。
「これはどこの宗教関係の高校だろう?」
「あれ・・・?これ・・・?『若き血』!? えっ!?これ、塾高!!??」
まさにこのような感じで驚いてしまいました。
それにしても、あれだけ多くのOBOGが甲子園に押しかけて応援歌をあれほどの大声で歌う学校って他にありますかね。
しかも慶應義塾高校は男子校ですから、女性はそもそもいないはずなのにそれでも大勢の女性がいらっしゃいました。
ということは塾高以外の慶應義塾出身者も多く駆けつけていたということです。
そしてそんな彼らの熱狂的な愛校心を目の当たりにした私は、「慶應 税理士」イケるな・・・!と思ったのでした。
ちなみに「慶応」ではなく「慶應」と表記しているのは意図的にそのようにしています。
その理由については慶應義塾OB・OGの方であれば説明しなくてもなんとなくご理解いただけるかと思います。
私が期待しているような「慶應出身の税理士を探している方」がいらっしゃるとすれば、その方は「慶応 税理士」ではなく「慶應 税理士」と検索されるものと確信しております。
反対に「慶応 税理士」と検索する人は、何か他のことを調べるためにそのようにされている別枠の方のような気がします。
学生時代の思い出
ここまでお読みいただき誠にありがとうございます。
もしいらっしゃった場合に備えて、せっかくですからついでに私の慶應義塾大学時代の思い出をご紹介します。
税理士を目指し始めた頃から勉強をかかさないようになりましたが、学部時代はさほど勉強には熱心ではありませんでした。
経済学部
私は慶應義塾大学の経済学部経済学科に在籍していました。
かなりオブラートに包んだ言い方をすれば試験前の「ノート集め」と「過去問集め」には熱中していました…
そして成績表では、積極的にCを集めていました…
無事に留年することなくストレートで卒業することができたとはいえ、3年生から4年生に上がるときはギリギリの状況でした。
3年生の後期では本当に追い込まれて必死に試験勉強をしたことを覚えています。
(その後の税理士になるための勉強と比べたらまったく何てこともなかったのですが…)
正直なところ、今となってはもっと学部時代にも真面目に勉強しておけばよかったなと後悔しています。
サークル
慶應義塾大学時代は、クリアバドミントン同好会というサークルに所属していました。
サッカーなどのサークルも回りましたが、居心地がよかったため結局そこに落ち着きました。
主な活動内容はお酒を飲んではしゃぐことでした。
今思えば本当によくあれだけのお酒を飲んでいたなと思います。
今どきの大学生からしてみれば信じられないことでしょうね。
当時の大学生はまだまだお酒をガブガブ飲んでいましたが、ちょうど私が大学を卒業した後に入れ替わりで入学してきた世代くらいから急激にお酒の飲み方がマイルドになったようです。
ちなみにバドミントンはちっとも上達しませんでした。
ゼミ
慶應義塾大学経済学部に在籍していたころは、瀬古美喜ゼミに所属していました。
専攻は、都市経済学でした。
都市経済学という学問は、都市が形成されていくプロセスについて経済的観点から研究するというものです。
当時学んだ内容を日本における現状と照らし合わせると、グローバルな資金流入による不動産バブルという視点が欠けていたと思います。
外国人が投機目的で購入するという理由でタワーマンションが乱立するとは想像ができませんでした。
バブルが絡むとどうしても行動経済学寄りになってしまうため、この現状を都市経済学だけで描写するのは難しかったかなという印象を持っています。
瀬古ゼミは1学年に20人に近い学生がいるという珍しい大所帯のゼミでした。
そこで私は外ゼミ代表を務めていました。
特に立候補したわけでもなく、自己紹介のスピーチがおもしろかったという理由で推薦されたため引き受けました。
瀬古ゼミでは瀬古先生の都市経済学という科目が必修に指定されていました。
恥ずかしながら、私たちの世代では3年生のときにその単位を取得することができなかったメンバーが3名も出現してしまいました。
私はそのことについて、ゼミ代表として心を痛め深く反省したことをよく覚えています。
なお、3名のうちの1人は私でした。
(無論、4年生のときに再履修してしっかり単位を取り直しました。)
ところで、瀬古ゼミの同期には私を含め3名も税理士がいます。
しかも3名とも公認会計士を経由して税理士資格を取得したのではなく、税理士試験に合格して税理士になった純粋培養の税理士です。
おそらく、1学年から3名も試験組の税理士を輩出するというのは、慶應義塾大学経済学部のゼミ史上最多記録であると勝手に考えています。
以上、慶應義塾出身の税理士川畑英之のことを徒然と紹介させていただきました。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
もしご興味をもっていただけましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ慶應義塾大学出身の税理士が提供する税務顧問と節税戦略
慶應義塾大学経済学部出身の税理士として、税務顧問・節税戦略の両面から事業者様を総合的にサポートいたします。学閥や人脈を重視する慶應出身の事業者様に向けて、信頼性の高いアドバイスと実行可能な節税対策を提供。税制改正への柔軟な対応、税務コンプライアンスの確保、経営目線での財務サポートなど、単なる申告業務を超えた価値あるサービスをお届けします。
税務顧問サービスで経営を強化
経営状況に応じた柔軟な税務プランニング
経営環境が日々変化する中で、企業には柔軟かつ戦略的な税務プランニングが求められます。私は慶應義塾大学出身の税理士として、経営者の意図や市場環境、財務状況を丁寧にヒアリングし、税務だけにとどまらず、資金繰りや投資計画も視野に入れたトータルな税務計画を立案します。たとえば、利益変動に応じた役員報酬の調整や、期末に向けた節税対策の検討、決算対策としての固定資産投資や備品購入のタイミング管理など、企業のキャッシュフローに直結する判断を支援いたします。また、税制改正が頻繁に行われる現在、最新の制度に基づいた提案も迅速に行う体制を整えています。
税務コンプライアンスとリスクマネジメントの実践
税務コンプライアンスを軽視すれば、税務調査や追徴課税のリスクが高まります。当事務所では、申告内容の精査に加えて、帳簿・証憑類の整備や保存体制の確認など、実務的なリスクマネジメントに注力しています。定期的な税務レビューを通じて、誤りや漏れの早期発見・是正を行い、税務署からの問い合わせや税務調査にも冷静かつ自信を持って対応できる状態を維持します。さらに、事業承継やM&Aを控える法人には、特有の税務リスクに備えるためのシミュレーションも提供。信頼性ある経営を支える税務顧問サービスとして、経営者様の「もう一人の参謀」となることを目指しています。
節税対策の基本と応用
法人税・所得税における節税の着眼点
節税とは単に税額を減らすことではなく、企業の成長と財務の健全化を実現する手段でもあります。まず基本となるのは、法人税・所得税の構造を理解し、適切な控除や特例を最大限に活用することです。例えば、青色申告特別控除、繰越欠損金の控除、交際費の一定額損金算入など、制度を正確に把握することで、正攻法の節税が可能になります。個人事業主やフリーランスの方であれば、事業的規模の判定を意識しつつ、家事関連費との区分管理や、経費の適正化を進めることが効果的です。申告書の作成段階でのチェックポイントを整備し、節税の「見落とし」を防止することも重要です。
設備投資・役員報酬・福利厚生を活用した節税戦略
応用編として、法人特有の戦略的節税として注目されるのが、設備投資や役員報酬の調整、福利厚生の活用です。たとえば、一定の生産性向上設備を導入すれば、即時償却や税額控除の適用が受けられるケースがあります。これは中小企業経営強化税制などの制度が根拠となっており、事前申請や証明書の取得が必要です。また、役員報酬は定期同額給与や事前確定届出給与の要件を満たすことで損金算入が可能となり、法人税と所得税のバランスを調整できます。福利厚生については、従業員への住宅手当、社宅提供、研修制度、健康診断費用など、要件を満たせば経費計上が認められます。こうした節税策は、税制改正の影響を受けやすいため、最新情報の把握と適用判断に専門家の関与が不可欠です。慶應義塾大学出身の税理士として、私は事業者様の目線に立ち、長期的な視点で節税をサポートいたします。
個人事業主の節税対策については下記のページで詳しく解説しています。
会計ソフト導入支援と経理代行
自社に最適な会計ソフト選びと初期導入支援
会計ソフトの導入は、企業の経理業務効率化と財務の可視化を実現する第一歩です。しかし、ソフトの選定を誤ると業務フローに支障をきたし、逆に負担が増えるケースもあります。私は事業規模・業種・従業員数・将来的な拡張性を考慮し、freee、マネーフォワード、弥生会計などの中から最適なソフトを提案します。選定後は初期設定、勘定科目のカスタマイズ、操作研修までを一括サポート。仕訳の自動化、レシート読取機能、クラウド連携などの機能活用により、入力作業の大幅削減を実現し、経理の「見える化」を後押しします。また、税理士が事前にチェックポイントを設定することで、決算時の作業も格段にスムーズになります。
経理業務の効率化を実現するアウトソーシング支援
日々の経理処理に追われている事業者様にとって、経理代行はコスト削減と品質向上を両立する選択肢となります。特に売上規模の拡大に伴い、経理ミスが命取りになるケースが増えている今、信頼できる外部委託先の存在は不可欠です。当事務所では、領収書や請求書の整理、仕訳入力、月次・四半期ごとの試算表作成、年末調整や法定調書作成まで、業務ごとに柔軟な代行プランを提供。クラウドソフトとの連携により、リアルタイムでの財務状況把握が可能となり、経営判断のスピードも向上します。さらに、税務署提出資料や金融機関提出用の決算書作成まで一括対応可能です。煩雑な業務を手放し、経営に集中したい方にとって、経理アウトソーシングは非常に有効な選択肢です。
慶應卒税理士が解説する確定申告と税務調査対応
慶應卒の税理士が、確定申告や税務調査に関する不安を解消し、スムーズな対応をサポートします。慶應義塾ご出身の個人事業主や法人代表の皆様が直面する複雑な申告業務や、税務署からの問い合わせ、調査の流れに対して、豊富な経験を活かしたアドバイスと実務支援を提供。信頼できる相談相手として、安心と納得のある対応をお約束します。
確定申告で押さえるべき基本と実務
所得税の基本構造と控除活用による節税
所得税は累進課税制度で構成されており、所得が高くなるほど税率も上がります。したがって、課税所得をいかに適正に抑えるかが節税の鍵となります。まず重要なのは、各種控除制度の正確な活用です。基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、寄附金控除など、利用できる控除を網羅的に検討し、申告に反映させることが必要です。また、青色申告を選択している場合には、最大65万円の青色申告特別控除を活用することにより、大きな節税効果が見込めます。事業所得がある方は、家事関連費との按分管理を徹底することや、減価償却資産の取得時期を調整するなど、実務的なテクニックも活用できます。
個人事業主の青色申告については下記のページで詳しく解説しています。
確定申告書作成から提出までの実務フロー
確定申告は、単なる書類提出ではなく、所得の計算から納税まで一連の手続きを要する重要な業務です。まずは1年間の収支を正確に記帳し、必要な証憑(領収書、請求書、源泉徴収票など)を整理するところから始まります。そのうえで、会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)を用いながら、所得計算と申告書作成を進めていきます。青色申告者は損益計算書・貸借対照表の添付も必要です。提出方法には、e-Taxによる電子申告と、紙での書面提出があります。電子申告の場合、還付までの期間が短縮され、添付書類の省略も可能となるため、近年は利用者が急増しています。提出期限は通常3月15日ですが、還付申告は過去5年まで遡って申請可能です。正確な申告を行うことが、税務署との信頼関係にも直結します。
電子申告と税務署対応のポイント
e-Taxの使い方と導入のメリット
e-Tax(イータックス)は国税庁が提供する電子申告システムで、近年ますます利用者が増加しています。e-Taxを活用することで、確定申告の提出が遠隔地から可能となり、税務署に行く手間を省けるだけでなく、添付書類の一部省略、還付までの期間短縮、過去データの再利用など多くの利点があります。ご自身または自社において導入される場合にはマイナンバーカード、ICカードリーダー、またはスマートフォン対応の認証環境が必要ですが、freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトとの連携も可能です。
税務代理による導入に関しては、利用者識別番号の取得方法から申告書の送信まですべてサポートいたします。この場合は税理士しかシステムを操作する必要がないため、e-Taxの知識がない事業者様でも安心していただけます。
税務署からの照会に備える対応力
申告後に税務署から届く「お尋ね」や「確認書類提出依頼」に戸惑う方は少なくありません。これらの照会に対しては、落ち着いて対応することが重要であり、あらかじめ証憑類や記帳データを整理しておくことが防衛策となります。たとえば、医療費控除や寄附金控除を申請している場合には、領収書や証明書の整合性をチェックし、提出準備をしておくべきです。また、e-Tax経由でも税務署からメッセージボックスに通知が届くため、定期的な確認を怠らないことが求められます。当事務所では、これら照会対応のための事前シミュレーションや書類準備、税務署との連絡代行にも対応可能です。慶應義塾大学出身の税理士として、正確性と信頼性の高いサポートを提供し、税務当局との円滑な関係構築を支援いたします。
税務調査への備えと当日の対応
税務調査の流れとチェックされやすいポイント
税務調査は原則として事前通知が行われ、調査官が企業や個人事業主の事務所を訪問して帳簿や証憑書類を確認する形式で実施されます。通知から実施までは通常1〜2週間の猶予があり、その間に準備を進める必要があります。調査では、売上の計上時期・方法、経費の妥当性、役員報酬・給与の支給状況、交際費の使途、貸付金・仮払金の処理などが重点的に確認されます。特に現金取引や、私的支出の混入が疑われる費用は厳しくチェックされる傾向があります。調査官の質問に対する回答内容や、証憑の提示態度も重要な判断材料とされるため、事前の準備と心構えが必要です。
帳簿・証憑管理と事前準備の具体例
税務調査に備えるためには、日頃からの帳簿管理が不可欠です。取引ごとの仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳・買掛帳の整備を行い、会計ソフトでの記帳を正確に維持することが基本となります。また、証憑書類(領収書・請求書・契約書など)との整合性を確保し、日付や金額、支払先が一致しているかを確認しましょう。紙媒体での保存だけでなく、電子保存のルールにも対応できる体制づくりも今後ますます重要になります。当事務所では、税務調査を想定した模擬チェックや事前ヒアリングの実施、資料の整備支援などを提供しています。調査当日には立会いも可能で、調査官とのやり取りに不安がある方にとっては大きな安心材料となります。慶應出身の税理士として、信頼と実績に基づくきめ細やかなサポートを行います。
税務調査対策については下記のページで詳しく解説しています。
慶應OB税理士がサポートする法人設立支援の流れ
慶應OB税理士として、信頼できるパートナーシップを築きながら、法人設立の構想から実行まで一貫して支援いたします。人脈を重視されるお客様にとって、同じ慶應出身という安心感と、豊富な経験に裏打ちされた実務支援が強みです。設立に伴う税務手続きや届出、将来の資金調達や節税戦略を視野に入れた法人設計を、丁寧にサポートいたします。
法人化のメリットと検討ポイント
節税・信用力アップ・資金調達への影響
法人化にはさまざまなメリットが存在します。まず代表的なのが節税効果です。法人にすることで、所得を分散し法人税率で課税されるため、一定の利益水準を超えた場合には所得税よりも税率が低く抑えられることがあります。さらに、給与所得控除を活用して、役員報酬として所得を分配することで、個人としての税負担軽減も図れます。次に、法人格を持つことで社会的信用力が向上し、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。これにより、資金調達の可能性も広がり、事業拡大を見据えた体制構築に有利に働きます。対外的な信用力は、新規取引の獲得や助成金申請の際にも大きなアドバンテージとなります。
法人化のタイミングと注意点
法人化を検討する際には、タイミングが非常に重要です。たとえば、年間の所得が800万円~1,000万円を超える事業者の場合、法人化による節税効果が顕著に現れることが多くなります。ただし、法人化には設立費用(登録免許税や定款認証費用など)が発生し、さらに社会保険加入義務が課されるため、毎月の固定コストが上昇する点に注意が必要です。また、個人時代の資産・負債の取り扱いや、自宅兼事務所の名義変更など、法的・実務的な課題が生じることもあります。事業の将来性や事業承継を見据えた法人化のタイミングを見極めることが重要です。当事務所では、シミュレーションを用いた費用対効果の比較検討を行い、慶應出身の事業者様のステージに応じた最適な法人化プランを提案いたします。
法人化については下記のページで詳しく解説しています。
設立手続きの実務と必要書類
定款作成から登記完了までの流れ
法人設立の第一歩は、事業の目的や本店所在地、資本金、機関設計などを明記した「定款」の作成です。定款は公証役場で認証を受ける必要があり、この時点で印紙税として4万円がかかりますが、電子定款を選択すればこの費用を節約できます。定款認証後は、出資金を代表者名義の銀行口座に払い込み、通帳のコピーを準備。次に、法務局に登記申請書、定款、発起人決定書、印鑑届出書などを提出し、登記完了を待ちます。通常、登記完了には1週間程度かかり、完了後には登記事項証明書や法人印鑑証明書を取得できます。これらは銀行口座開設や税務署提出書類に必要となるため、早期取得が望まれます。
法人設立時に提出すべき税務関連書類
法人設立後は、所轄の税務署へ複数の税務関連書類を期限内に提出する必要があります。代表的なものとして、「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」などがあります。これらの提出期限は原則として法人設立の日から2ヶ月以内とされていますが、青色申告承認申請書については、初年度の事業年度終了日の3ヶ月前までの提出が必要です。期限を過ぎると控除が受けられない等の不利益が発生するため、注意が必要です。当事務所では、必要書類のリストアップから作成、提出代行まで一貫してサポートし、提出漏れによるトラブルを未然に防ぎます。慶應義塾大学出身の税理士として、制度に精通した専門知識をもとに、安心・確実な法人設立の実現をお手伝いします。
設立後に必要な届出・手続き
税務署・都道府県税事務所・年金事務所への届け出
法人設立後は、さまざまな官公庁への届出が必要です。まず税務署には「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。これらは設立後2ヶ月以内が原則となっており、遅れると青色申告の適用が認められなかったり、罰則が科される可能性があります。さらに、法人住民税や事業税に関する「法人設立届出書」を都道府県税事務所・市区町村にも提出する必要があります。これを怠ると、課税情報が正しく把握されず、後のトラブルの原因となることがあります。また、年金事務所へは「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出し、社会保険の適用事業所として登録する必要があります。適用要件は常時1名以上の従業員雇用であり、専従役員のみの場合でも対象になることがあるため、慎重な判断が必要です。
社会保険・雇用保険・労働保険の加入サポート
従業員を雇用する場合、社会保険に加えて雇用保険・労災保険(労働保険)の加入も義務となります。これらはハローワークや労働基準監督署に届け出を行い、事業所としての適用手続きを進める必要があります。提出書類としては「雇用保険適用事業所設置届」「労災保険概算保険料申告書」などがあり、設立直後は同時並行での手続きが必要となります。当事務所では、社会保険労務士とも連携し、これら労務関連の届出・申請を一括してサポート可能です。これにより、経営者の事務負担を軽減し、労務リスクの回避に貢献します。慶應義塾大学出身の税理士として、制度や実務に精通した視点から、設立後のスタートアップ期を強力にバックアップいたします。
FAQ よくあるご質問
慶應出身の税理士を選ぶメリットは?
慶應義塾大学経済学部出身者ならではの財務分析力で、税務と経営の両面から最適な税務プランニングを提案します。また、お誘いいただければお酒の席や麻雀(もう久しくやっていません)などに喜んで同席させていただきます。
消費税のインボイス制度で気をつけるべきポイントは?
2023年10月導入の適格請求書発行事業者登録制度では、適切な帳簿管理が必須です。当事務所では、会計ソフト導入支援や税務コンプライアンス強化策を提供し、スムーズな制度対応を実現します。
消費税のインボイス制度については下記のページで詳しく解説しています。
慶應OB税理士の無料相談は可能ですか?
初回60分無料相談をオンライン(Teamsによるビデオ会議)で実施しています。税務相談だけでなく、財務戦略など、慶應経済学部出身者ならではの視点で課題解決策を提案します。ぜひお気軽にお問い合わせください。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080−7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ